なぜ転校を決断したのか
我が家は、長女がプリスクールに通っていた頃から、海外のインターナショナルスクール(インター)に通わせてきました。
いくつかの学校を見学し、納得したうえで選んだ学校だったため、まさか同じ国の中で再び「転校」を考える日が来るとは、当初は想像もしていませんでした。
しかし、日々の送り迎えを通じて先生や子どもたちの様子、さらには保護者の雰囲気を肌で感じる中で、少しずつ“学校の質の変化”に気づくようになりました。
特にコロナ禍を経て、教員の入れ替わりや学校全体の方針に揺らぎを感じたことが大きかったです。
インターは「入学して終わり」ではなく、「通い続ける中での見極め」がとても大切だと改めて実感しました。
子どもたちが毎日を過ごす環境が、今も「安心して学べる場であるかどうか」。
そこに対して違和感が出てきたとき、私たちは転校という選択肢に向き合うことになったのです。
最初に、小学校として選んだインターの決め手
長女がプリスクールから小学校へ進学するタイミングで、わが家は一度目の転校を経験しました。
もともと通っていたスクールはプライマリーまで一貫で進める学校でしたが、幼児期に求める環境と、小学校で求める教育の質は別モノだと感じ、改めていくつかのインターナショナルスクールを見学し直しました。
■ カリキュラムの違いに注目
当時、候補となったインター校では主に以下の3つのカリキュラムが採用されていました:
- IB(国際バカロレア)
- ケンブリッジ式
- アメリカ式
この中で特に気になったのが、IB(PYP)カリキュラムでした。
IBは「探究型の学び」や「グローバル思考」を育てる教育として魅力的に感じる一方、抽象的な思考が求められる場面が多く、小学生には少し難易度が高いのでは?と感じました。
■ 小学生にはIBが早いと感じた理由
小学生の学びは、まだまだ「実生活とのつながり」や「具体的な体験」が中心であるべきだと私は考えています。
たとえば「分数」や「時刻」など、日常生活に直結する知識は、使いながら身につけることで理解が深まります。
そう考えると、IBのように抽象的なテーマを探究しながら学ぶスタイルは、先生のスキル次第で大きく左右されてしまうという懸念がありました。
特に、英語を学びながら他教科も同時に理解していく環境では、「分かりやすさ」と「指導力」は欠かせません。
■ ケンブリッジを選んだ当時の判断
最終的にわが家が選んだのは、ケンブリッジカリキュラムを採用している学校でした。理由は、以下の3つ:
- 教科の系統性と明確な到達目標があり、親としても成長を把握しやすい。
- 英語が母語でない子どもに対しても対応ノウハウが確立されていたこと。
- クラス構成や校風も穏やかで、安心して通わせられると感じたこと。
当時は「これで間違いない」と思えるほど納得して入学を決めました。
まさか数年後に再び転校を考えるとは夢にも思っていませんでしたが、子どもの成長とともに「その時ベストだと思った選択も、いつまでもベストとは限らない」ことを学ばせてもらいました。
転校を決めた理由と不安材料
入学当初は「ここで小学校生活を6年間過ごすのかな」と思っていたわが家。
しかし、数年たつにつれて、「あれ…何かが変わってきている?」という小さな違和感が積み重なり、最終的には転校という選択肢に至りました。
その背景には、いくつかの明確な“質の変化”がありました。
■ 現地訛りの強い教師が急増
まず気になったのは、先生の英語の質でした。
以前は発音がクリアで、子どもたちが安心してまねできる英語環境が整っていたのですが、現地訛りがかなり強く、聞き取りづらい先生が増えてきたのです。
もちろん、訛りがあるから悪いというわけではありません。
でも、英語習得の基礎を固めている段階で、正確な音をたくさんインプットしてほしいという親としての思いがありました。
学校の方針として発音や表現の統一性にこだわりが見えなくなってきたことに、不安を感じ始めました。
■ 教員ライセンス・経験の不透明さ
次に感じたのは、教員の「質」自体のばらつきでした。
ある先生は非常に熱心で指導力もありましたが、別の先生は「教員免許あるのかな?」「教育経験あるのかな?」と感じるような対応もちらほら…。
「インター=質が高い」と思い込んでいた自分に反省する場面も増えてきました。
ローカル採用の先生が多くなることで、全体的な教育のクオリティが安定しないというのは、インターナショナルスクールあるあるかもしれません。
ただ、それを見過ごすわけにはいきませんでした。
■ 学費とのバランスが崩れていく
そして最後に一番大きな決断理由になったのが、「高額な学費」と「得られる教育内容」のバランスが崩れていると感じたことです。
年間で数百万円近くかかる学費。
それに対して、授業内容や先生の質、サポート体制を照らし合わせたとき、「この金額に見合ってる?」と疑問が湧いた瞬間から、転校を真剣に考え始めました。
もちろん、完璧な学校などありません。
でも、少なくとも「今うちの子にとって必要な学び」が得られるか?を冷静に見直す必要があると感じたのです。
実際に重視した“転校先”の選び方3つ
「じゃあ、次はどこに通わせる?」
この問いに向き合ったとき、わが家が大切にしたのは“フィーリング”ではなく“条件の見える化”でした。
インターだからって全部安心、という時代ではありません。
だからこそ、親として確認したポイントははっきりと3つあります。
教師の国籍と英語ネイティブ率
訛りの強さも大事ですが、それ以上に感じたのは“英語ネイティブとしての感覚の違い”でした。
たとえば、英語のニュアンスや文化的背景、日常的な表現の自然さ。
これらは「英語を話せる」だけの先生ではなかなかカバーできない部分です。
実際に見学した中でも、先生の半数以上が英語ネイティブで構成されている学校は、子どもたちの話す英語の質が明らかに違っていました。
ネイティブだから良いという単純な話ではなく、“教える英語”と“使う英語”のバランス感覚を見極めることが大切だと感じました。
教員ライセンスの有無と経験年数
これは外せませんでした。
ライセンスがあっても経験が浅い先生、経験はあってもライセンスが不明な先生、いろいろなケースがありました。
その中で、「ライセンスあり × 経験豊富」の先生が多い学校は、授業の設計や子どもの接し方に一貫性があり、安心感がまるで違いました。
特にうちの子どもたちは「先生が何を求めてるのか分からない」と不安になるタイプ。
だからこそ、明確な教育スタンスと実績を持つ先生がいることは、転校先の大きな判断材料になりました。
日本人比率と“母国語OK”の校風
これも大きなポイントでした。
「英語が伸びる環境」に見えて、実は母国語ばかりが飛び交っている——そんな場面、何度も見てきました。
日本人比率が高すぎると、子ども同士の会話がどうしても日本語になってしまい、“英語を使わざるを得ない”という状況を作るのが難しくなります。
もちろん、「安心して話せる存在」がいることは大切ですが、それが英語環境の成長を妨げるようでは本末転倒です。
なので、とにかく日本人が少ない学校に絞りました。
さらに、「母国語は校内ではNG。見かけたらその都度、英語で話すように促す。」という学校だけを候補に挙げました。
子どもですから、自分が英語よりも母語が強ければ、母語が通じる友達とは母語で話そうと思うのは自然なことだと思います。
その気持ちはとてもよくわかります。
だからこそ、ただ注意したり叱るみたいなこともちょっと違うのかなと思っていました。
先生やスタッフが「英語で話そうよ!」と促してくれるような雰囲気があるといいなと思いました。
現インターで感じた“限界”
転校を検討しはじめた最大のきっかけは、子どもたちの“学びの質”に影響が出はじめたことでした。
インターナショナルスクールという環境において、言語の壁は避けて通れません。
でも、そのバランスが大きく崩れた瞬間に、私の中で「限界かもしれない」と思うようになったのです。
娘たちが「通訳役」にされる日常
英語がある程度できる娘たちは、クラスに新しく入ってきた日本人の子たちのサポート役=通訳役として自然と期待されるようになりました。
もちろん、困っている子を助けるのは大切なこと。
でもそれが日常的に、しかも授業中にも起きるとなると話は別です。
「なんで、わたしがずっと通訳しなきゃいけないの?」
「自分の勉強に集中したいのに…」
そんな言葉を娘から聞いたとき、私の中でもモヤモヤがはっきりと“危機感”に変わりました。
英語が分からない子の増加 → 授業の崩壊
ここ数年で、英語がほとんど話せないまま入学してくる生徒が増えている現実もあります。
しかも、インターに入れる親の多くは「いずれ英語ができるようになればOK」と考えているため、入学時の英語力にはあまり厳しくありません。
その結果、授業中に「え?なに?」と繰り返し聞き返す子が複数人いる状態が普通になり、先生も一つひとつ丁寧に説明し直す必要が出てきます。
これは、授業のテンポが崩れ、他の子の理解や集中にも悪影響が出てくる構造です。
日本語での暴言・いじめに先生が気づけない
さらに深刻なのが、日本語での悪口や暴言が先生たちに伝わらない問題です。
実際に、娘たちが日本語で意地悪を言われたり、見えない形で排除されたりする経験もありました。
英語なら先生も注意できます。
でも、母国語でのやりとりが放置されてしまえば、“いじめ”が可視化されにくくなるのです。
これは英語が話せない子にとっては「嫌なことがあったら先生に言ってね」と伝えていても、
「でも、英語で説明するの難しいし、伝わらなかったらどうしよう…」
と、言い出せない子も多いと思います。
限界を感じたからこそ、“転校”という選択肢を再検討
インターにはインターならではの良さがあります。
でも同時に、多国籍・多言語環境ゆえの課題も確実に存在しています。
「このままでいいのかな?」
「もっと娘たちが安心して、のびのび学べる場所があるんじゃないか?」
そんな想いが日に日に大きくなり、私たちは再び転校という選択肢に目を向けることにしました。
転校後に期待していること
転校を決めたからには、当然そこに「もっと良くしたい」という願いがありました。
娘たちが、“本来の学び”にもっと集中できる環境で過ごしてほしい――それが、私たち家族のいちばんの願いです。
より集中できる“英語環境”を
前のインターでは、英語がほとんど分からない子たちへのサポートに時間が割かれ、全体の授業の進行がかなりゆっくりになっていました。
その中で、ある程度英語ができる子たちが、物足りなさや退屈さを感じていたのも事実です。
新しい学校では、英語ネイティブの先生が中心となって授業が進むことや、一定の英語力が求められる入学基準があることが決め手でした。
「娘たちが英語だけに“気を取られすぎない”ことで、思考や創造に集中できる」
そんな環境が整っていることを、親として大きく期待しています。
まとめ:海外インターは「見て、感じて、決める」
インターナショナルスクールに通わせるって、なんだかキラキラした選択に思われがちですが、
実際に子どもが過ごしている“日常”にこそ、すべてのリアルが詰まっています。
「どんな先生が教えてくれているのか?」
「子どもたちは、どんな言語で、どんなテンションで、何を学んでいるのか?」
数字やカリキュラム、パンフレットの言葉だけでは分からない“肌感覚”を、ちゃんと親の目で見て、耳で聞いて、心で感じることが大切だと、私たちは実感しました。
学校は、変えられなくても「変えられる」
「どこの学校も完璧じゃない」――これは、たしかに真実です。
でも、「じゃあ諦める?」と言われたら、私は首を横に振ります。
学校の仕組みや文化を一夜で変えることはできなくても、私たち親が選び直すことはできる。
それが、今回の転校で強く感じたことでした。
子どもが、自分らしく学べる場所を
どんなに高い学費を払っていても、
どんなに有名な教育カリキュラムが導入されていても、
子ども自身が安心して、前向きに学べる環境じゃなければ意味がない。
その“肌に合う環境”を見つけるには、親のアンテナと行動力が不可欠です。
だからこそ、迷っている親御さんには伝えたいんです。
海外インターに通わせているからといって、我慢や違和感を飲み込まないでいいんです。
「いまの学校で本当にいいのかな?」と感じたら、ぜひ立ち止まって、見て、話して、考えてみてください。
子どもの未来のために“転校”という選択肢を持つこと自体が、すでに立派な行動です。
こちらも併せてどうぞ👇️
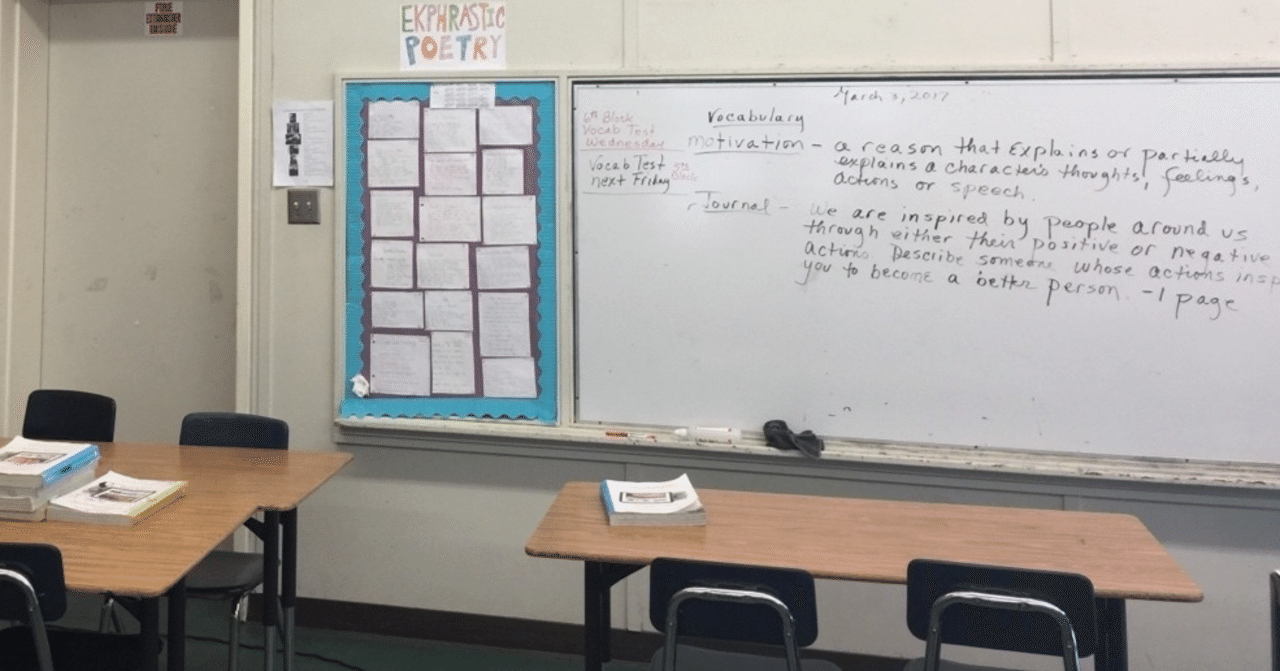





コメント