夏休みは、子どもたちにとって学校では体験できない新しいことに挑戦する絶好の機会です。今年の我が家では、それぞれが少し背伸びをして目標に向かう“挑戦の夏”をテーマに過ごしています。
長女は、ずっと憧れていたKindleBookでのエッセイ出版に向けて執筆を始めました。自分の考えや感じたことを言葉にする作業は決して簡単なものではありませんが、一歩ずつ進む姿からは確かな成長を感じます。彼女の書き上げた文章を読むたびに、親として驚きと喜びが入り混じった気持ちになります。
一方、次女は長女と一緒に夫の法人のロゴ制作に挑戦しています。まだ小さな手で描く線にも、次女ならではの独特な感性が光ります。家族全員でアイデアを出し合い、形にしていく過程は、私たちにとっても新鮮な経験です。
この記事では、エッセイ執筆とロゴ制作という、それぞれが取り組む挑戦の舞台裏をご紹介します。子どもたちが挑戦を通じて得た学びや、家族で共有した貴重な時間について、ぜひお楽しみください。
長女の挑戦:エッセイ執筆で目指すKindle出版
なぜエッセイ執筆を始めたのか?
長女が執筆に興味を持ち始めたのは、本を読むのが好きだったことです。多くの本を読み、自然と本の著者に憧れるようになりました。でもまだ11歳。まさか自分が著者になれるとは思っていません。
そこで私から「Kindleだったら自分のエッセイを自分で出版することもできるよ。やってみる?」と提案しました。少しだけ考えた長女は「やってみたい」と。今年の夏は“本を出版する”という目標を掲げ、KindleBookでのエッセイ出版に挑戦することを決めました。
目標を決めたものの、最初は『何を書けばいいの?』と戸惑う様子もありました。でも、普段から日記や作文を書いていた彼女にとって、“自分の気持ちを言葉にする”ことは決して初めてのことではありません。少しずつアイデアを出しながら、自分が本当に伝えたいテーマを探していく姿は、見ていて頼もしさを感じさせます。
エッセイの執筆を進める中で、彼女が選んだテーマは“自分の経験と感じたこと”。身近な出来事や海外生活での発見、学校での挑戦など、11歳なりの視点で綴る内容は、親としても新鮮で心温まるものばかりです。
もちろん、書き進める中で壁にぶつかることもあります。『この言葉で伝わるかな?』『もっといい表現があるかも』と悩む姿も見られますが、それもまた成長の証。彼女が真剣に向き合っている姿勢は、エッセイ執筆という挑戦の意義そのものを物語っています。
現在、執筆はまだ途中段階ですが、少しずつ形になりつつあるエッセイを見ながら、彼女自身も完成への期待を膨らませています。この挑戦が彼女にとって特別な夏の思い出となるよう、親としてもサポートを続けていきたいと思っています。
執筆の進め方と工夫
エッセイ執筆を始めた長女にとって、毎日のスケジュールを決めることは挑戦の第一歩でした。まだ11歳の彼女にとって、“計画的に進める”こと自体が学びの一環です。私たちは一緒に『1日30分の執筆時間』をルールとして設定し、無理なく進められるペースを大切にしています。
まずは、彼女のこれまでの人生で住んできた国別に、特に記憶に残っていることを一緒に挙げていきました。とにかく長女にとって印象的だった出来事が何なのかはこのアイデア出しの部分である程度決まっているのかもしれません。
心が動いたから、記憶に刻まれるものですよね。
アイデア出しの段階で、長女は印象に残った出来事を一つずつ言葉にしていきました。心が動いた瞬間を思い返す中で、自分にとって特別なエピソードが次第に浮かび上がってきます。そのメモを元に、彼女は少しずつ文章を書き始めています。
1日30分という短い時間でも、集中して取り組むことで、確実にエッセイが形になっていくのが彼女自身の励みになっているようです。進捗はゆっくりですが、確実に一歩ずつ前に進んでいます。
挑戦を通じて見えた成長
エッセイ執筆に取り組む中で、長女の成長を感じる瞬間が増えてきました。最初は『何を書けばいいかわからない』と悩んでいた彼女も、少しずつ自分の言葉で気持ちを表現できるようになっています。
特に、印象的だったのは、自分の考えを相手に伝えることの大切さに気づいた瞬間です。『この言葉だと、読んだ人に伝わるかな?』と自分で問いかけながら文章を直す姿を見て、彼女の中で“伝える”という意識が芽生えているのだと感じました。
まだ途中段階ではありますが、執筆を通じて少しずつ自信をつけ、成長する姿は、親としてとても誇らしいものです。
次女の挑戦:初めてのロゴ制作に挑戦
ロゴ制作に参加することになった理由
次女がロゴ制作に参加することになったのは、夫の法人設立がきっかけでした。
私は、この夫の法人設立をきっかけに子供たちが「会社」というものを知っていく最高の機会だと感じていました。『せっかくなら子供たちにロゴデサインに挑戦させてみない?』という私の提案に夫も『俺も同じこと考えてたよ!』と意気投合。
早速子供たちに提案すると、興味津々でした。そういうわけで、次女も長女と一緒にロゴデザインに挑戦することになりました。
次女はもともと絵を描くのが大好きで、自分のアイデアを形にすることが嬉しそうです。『どんな形がいいかな?』『色はどれがいいかな?』と、デザインの基礎に触れる体験が新鮮なようです。彼女の独特な感性が、家族全員を驚かせる場面も少なくありません。
家族全員で作るロゴのアイデア
ロゴ制作を始めるにあたって、まずは有名なロゴをいくつか調べてみました。子どもたちは形やデザインの意味に興味を持ち、それらを組み合わせた案を次々と出してきました。しかし、それらはどこか単調で、オリジナリティが感じられないものでした。
そこで私たちは、『ロゴに込める思いが大事なんだよ』と話し合いました。『この会社を象徴するものは何か』『ロゴを見た人に何を伝えたいのか』を考えることの重要性を伝えると、子どもたちはその指摘を真摯に受け止め、より深く考えた案を出すようになりました。
これまでに3度、子どもたちによるロゴ案のプレゼンの場を設けています。1度目と2度目は、自分たちで一生懸命スライドを作成し、ロゴ案の意味や形に込めた思いを丁寧に説明してくれました。その熱意は素晴らしいものでしたが、私たちの指摘を受け、さらに修正を重ねることになりました。
3度目のプレゼンは、夫が帰国を控えていたため時間が限られており、紙に手書きで案をまとめて発表する形になりました。それでも、次女は『家族が一緒に頑張っている感じを出したい』と語り、長女は『もっとシンプルで覚えやすい形がいい』などと意見を出し、洗練されたデザインを描き上げていました。
試行錯誤の中で壁にぶち当たっているかんじがする日もあります。次女はまだ7歳なので、シンプルに飽きてしまったりする日も珍しくありません。
長女には『あなたがリーダーだからね。次女をやる気にさせることも、次女ができるように噛み砕いて指示してあげることもリーダーの仕事だよ。』と伝えています。
まだ完成には至っていませんが、家族全員がそれぞれの思いを形にしようとするこのプロセスこそ、ロゴ制作を通じた最大の収穫だと感じています。
ロゴ制作が教えてくれた大切なこと
ロゴ制作を進める中で、私たちは子どもたちにも報酬を支払うことにしました。二人の出したロゴ案が採用されたら、長女には7ドル、次女には3ドル。
長女がリーダーとしてプロジェクト全体をまとめる役割を担うため、そのような分配にしたのです。この金額は、長女に『いくら貰えると思ったらやる気が出る?』と尋ねた際に、『5ドルとか10ドルくらいかな?』と言ったのを参考にして決めました。
子どもたちはこの提案に納得し、それぞれの役割を全力で果たすべく取り組みを始めました。ところが、スタートしてみると長女から意外な提案が。『次女が意外と頑張ってるから、採用時の報酬は6ドルと4ドルにしてもいい?』と言ってきたのです。その一言に、私は感動しました。リーダーとしての責任を果たしながら、次女の努力をしっかりと評価し、公平性まで考えている姿に、成長を感じずにはいられませんでした。
こういうことを自分で感じで考えて実行に移してみる。これを体験することに一番の価値があると思っています。
次女もその提案を受けてさらにやる気を出し、どんな色や形がいいか、細かいアイデアをたくさん出してくれるようになりました。このエピソードを通じて、報酬の金額だけではなく、“お互いを尊重し、認め合うこと”の大切さを子どもたち自身が学んでいるように感じます。
まだロゴの完成には至っていませんが、このプロジェクトを通じて、子どもたちが“働く”ことの本質を少しでも理解する第一歩になればいいなと思います。この経験が、彼女たちにとってかけがえのない学びとなることを信じています。
家族全員で挑戦する楽しさと学び
夏休みの学びから得たもの
この夏休み、長女と次女はそれぞれにとって新しい挑戦に取り組み、たくさんの学びを得ています。ロゴ制作やエッセイ執筆は、単に「作る」「書く」だけではなく、それを通じて多くのことを考え、経験する時間のように思います。
次女は、自分のアイデアを出すことが楽しいと感じ、デザインに夢中になる一方で、時には『もうやめたい!』と投げ出しそうになることもありました。そんな時、長女が『ここまで頑張ったんだから、あと少しだけやってみようよ!』と声をかける場面がありました。次女はその言葉に背中を押されて再び頑張る姿を見せてくれました。
一方で、長女もリーダーとしての役割を通じて、新しい一面を見せてくれました。『どう伝えれば次女がわかりやすいかな?』と考えながら説明する様子や、『次女の意見をもっと聞いてみよう』と気遣いを見せる姿に、成長を感じずにはいられませんでした。
さらに、報酬の話をきっかけに、お互いの努力をきちんと評価し合うことを自然と学んでいたのも驚きでした。長女が『次女が意外と頑張ってるから、報酬を6ドルと4ドルにしたい』と言った時には、感動してしまいました。このやり取りは、子どもたちにとっても印象深いものになったはずです。
親として、こうした取り組みを通じて子どもたちが成長していく姿を間近で見られるのは、とても幸せなことです。この夏休み、家族全員でひとつの目標に向かって挑戦した経験は、きっと彼女たちの中でかけがえのない思い出として残ることでしょう。そして私にとっても、それを支える時間が最高の宝物になりました。
家族全員で共有した学びと喜び
この夏休みの挑戦を通じて、家族全員が「一緒に取り組む」ことの大切さを改めて感じました。
長女と次女が中心になってプロジェクトを進める中で、夫と私はサポート役に徹し、子どもたちが自分たちで考え、行動できる環境を整えることを心がけました。
例えば、ロゴ制作では、夫が自身の仕事の視点から『どんなデザインが印象に残るのか』をアドバイスし、私は子どもたちの意見を引き出す役割を担いました。具体的な指示を出さずに見守ることで、子どもたちが自発的に話し合い、試行錯誤を繰り返す姿が見られました。その過程で、親も『サポートの仕方』について多くの気づきを得ることができました。
エッセイ執筆では、長女と私のやり取りが日々の習慣になりました。一緒に考えながら新しい視点を見つける時間が楽しいものです。また、長女が『こう書くともっと伝わるかな?』と自分なりに工夫を重ねる姿に、彼女の成長を感じる場面もありました。書くことを通じて、彼女が自分の考えを整理し、自信を持てるようになるといいなと思います。
こうした経験を通じて学んだのは、「誰かの努力を認めることの大切さ」と「共通の目標を持つことが生み出す絆」です。ロゴやエッセイの完成を目指す中で、家族みんながそれぞれの役割を果たしながら一つの目標に向かう。この時間が、ただの夏休みを特別なものに変えてくれたのだと思います。
まだプロジェクトは終わっていませんが、私たち家族にとって、今回の挑戦がひとつの大きな財産になったことは間違いありません。この学びを次の機会にも活かしながら、これからも家族全員で新しい挑戦を続けていきたいと思います。

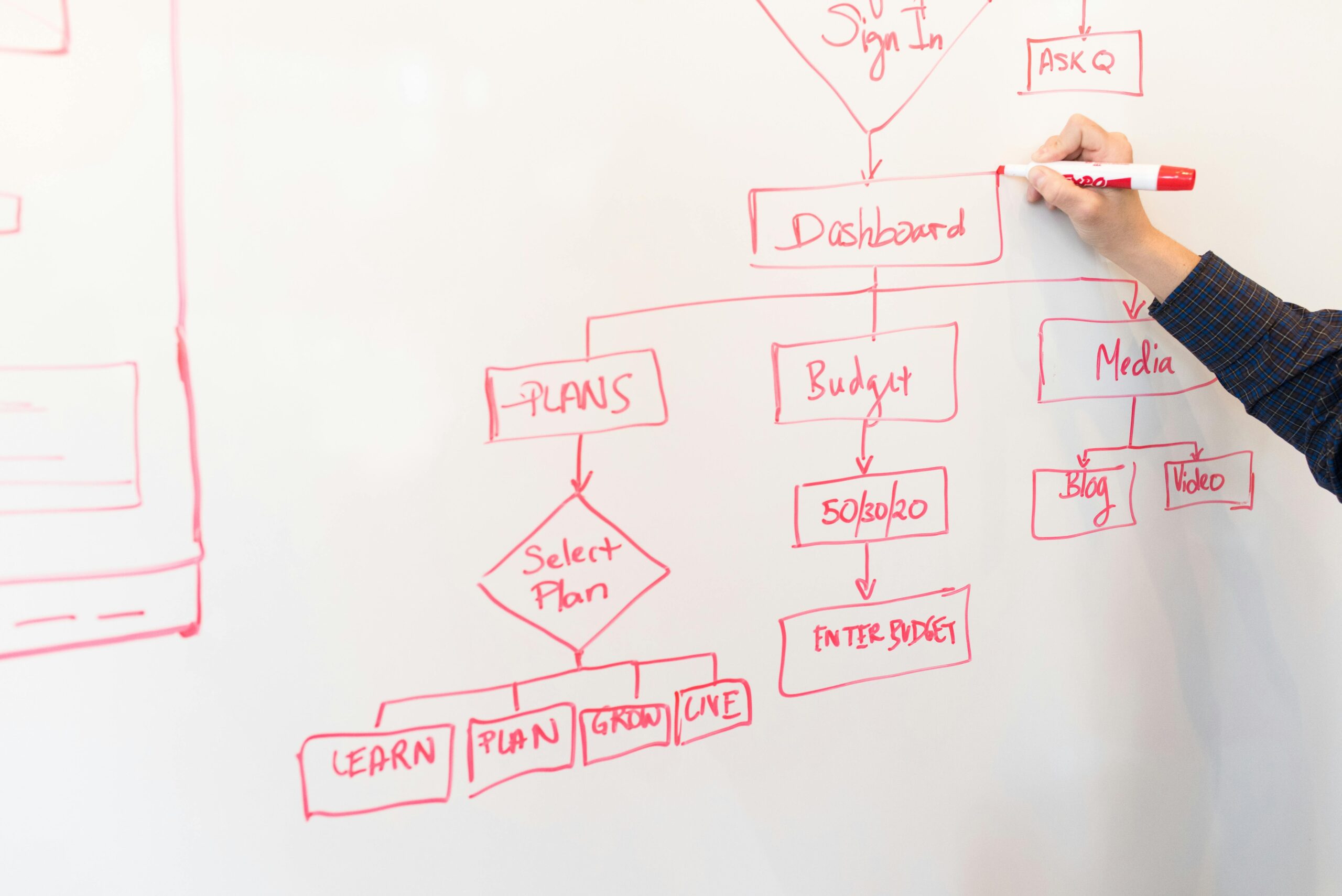


コメント